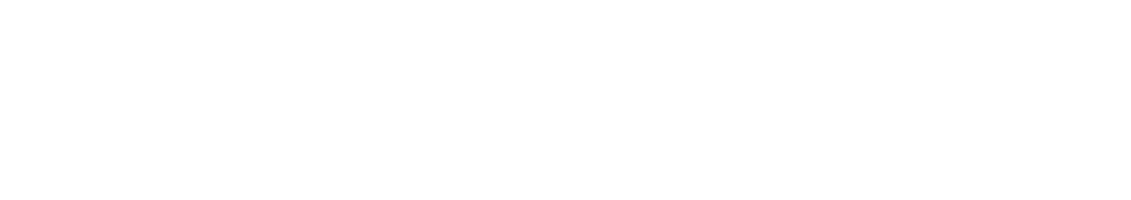KOWAKAMAI
幻の舞、
現代に蘇る。
それは、能、歌舞伎、浄瑠璃の源流となった、日本芸能の原点。
室町時代に一世を風靡し、歴史の狭間に姿を消した「幻の舞」。
若柳家三代にわたる宿命のもと、その神秘のベールが今、剥がされる。
歴史と文化
日本芸能の原点
幸若舞の起源は、その名が付けられる以前、今から約七百年以上前に遡ります。それは単なる一つの舞踊ではなく、日本の芸能史において根源的な役割を果たした「日本芸能の原点」と言われています。
能、歌舞伎、浄瑠璃といった、現在日本を代表する伝統芸能の数々に影響を与えたその様式は、まさに文化の源流の一つ。様々な芸能で使われている摺り足やトンと足を踏む動作は、天文学や陰陽道より取り入れられ、現代に続いています。
室町から江戸時代にかけ一世を風靡したのち、歴史の表舞台から姿を消したことから「幻の舞」とも呼ばれています。

精神と儀礼
神事としての舞

幸若舞の目的は、単なるエンターテイメントの追求ではありません。その根底には「自然との共存」という思想があり、神事から生まれた儀礼的・精神的な側面を強く持ちます。
舞の中には陰陽道や天文学の思想が取り入れられ、例えば北斗七星の形をなぞる動きは、邪気を払い、縁起をもたらす神事としての機能を果たしていました。演者が謡と踊りの両方を行うという特徴も、神に捧げる儀式としての純粋性を保つためのものだったのかもしれません。
代表的な演目
語り継がれる物語

敦盛 (あつもり)
幸若舞を語る上で欠かせないのが、日本の歴史上最も有名な逸話の一つと結びつく演目『敦盛』です。
織田信長が桶狭間の戦いへ出陣する際、かの有名な一節を謡い舞ったと伝えられています。これがまさしく、幸若舞の一つでした。
人間五十年、下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり
この逸話は、幸若舞が時の権力者にも愛され、歴史の重要な局面において舞われてきた、疑う余地のない歴史的正統性の証左です。

幸若三番叟 (こうわかさんばそう)
『幸若三番叟』は、古来より演目の幕開けで舞われる「祝儀曲」です。その目的は、五穀豊穣と子孫繁栄を願うこと。
振付は極めて象徴的で、足拍子で大地を固め、手に持った鈴で種まきを表現するなど、農耕儀礼に深く根ざした動きで構成されています。
歴史の遺物としてではなく、儀礼的な機能を持ち、今まさに復活しつつある「生きた伝統」。それが『幸若三番叟』なのです。
若柳家と幸若舞
三代の宿命

二代目 若柳吉三次
研究者として、復活を志した父
二代目吉三次にとって、幸若舞の復活は生涯をかけた悲願でした。彼は「縁の幸若舞研究者」として、その歴史と舞を深く探求。その情熱は、金王八幡宮宮司が「幸若舞の復活を志していました」と証言するほどのものでした。彼は、幻の舞が再び日の目を見る日を夢見た、偉大な革新者でした。
三代目 若柳吉三次
― 継承者として、父の遺志を舞う娘 ―
三代目にとって、幸若舞を舞うことは父の「遺言」を果たすこと。父が遺した膨大な研究を血肉とし、現代に生きる演者として、その魂を舞台上で具現化しています。「自らの祖先が生んだ幻の芸能を舞う」—その姿は、父の夢の集大成であり、三代にわたる宿命の物語の、まさにクライマックスなのです。
現代での活動
未来へつなぐ

東京コレクションにて、幸若舞『敦盛』披露

日比谷公園にて、幸若舞『幸若三番叟』披露

磯長山 叡福寺 聖徳太子1400 年御遠忌大法会にて幸若舞『和』奉納

富岡八幡宮にて、幸若舞「幸若三番叟」奉納

出雲大社にて、幸若舞「幸若三番叟」奉納
三代の時を超え、現代に蘇った幸若舞。
その物語は、まだ始まったばかりです。